|
1.はじめに
2002年7月に発表された「知的財産戦略大綱」は、そのおどろおどろしい名前と時代錯誤的な「知的財産立国」というキャッチコピーで長年の不況に疲れた産業界に喝をいれる一方、大学にはその中心的な役割を担うことを求めた。翌2003年10月1日国立大学法人法が施行され、国立大学は2004年4月1日、国立大学法人となった。このような背景の下で、国立大学は研究の成果を社会に還元するために産学連携に積極的に取り組むこととなった。そして産学連携を実りあるものとする上で不可欠であり、また、法人化により自由度を増した財務上の資源を増加し得る手段である「知的財産(主として特許)」を国立大学自らの手で管理していくこととなったのである。
このような時代のうねりのなかで「産学連携のパイオニア」を自負する大阪大学は、知的財産の創出、および移転にどのように取り組み、どのように運営しているのかを紹介するとともに、大学発の発明および技術移転に見られる問題点について触れる。
2.実学の大阪大学
大阪大学は
1 世界最高水準の研究の遂行
2 高度な教育の推進
など10の項目からなる大阪大学憲章を持つが、この中には大阪大学の生い立ちに関わる
社会への貢献
実学の重視
の2項目が含まれる。第1次世界大戦後、大阪の産業界は独自の工業技術の開発を推進することを目的に帝国大学の設置を提言した。しかし関西には京都帝国大学が既に存在することなどで受け入れられにくい状況にあった。そこで大阪産業界が財政支援を約することで認可が得られ1931年に医学部及び理学部の2学部でスタート、2年後に工学部が追加された。この様な誕生の背景にある地元産業界の支援に報いる事が重要であるとの認識が「社会への貢献」「実学の重視」の2項目を策定させる動機となっている。これらの項目が単なるお題目でないことは、地域住民、地元産業界への様々な形での貢献活動に顕著に表れている。実学という見地から見ると、企業等との共同研究件数は東京大学に次ぐ265件(2002年度)で、教官ひとり当たりの件数では首位の座を占める。
大阪大学には創立直後に設立された微生物病研究所、世界的に評価の高い蛋白質研究所など付属の研究機関が多数存在する。これらの中で産学連携に関わるものとして先端科学技術共同研究センター及びベンチャー・ビジネス・ラボラトリーがあった。前者は大学内外の共同研究及び起業の支援などを、また後者は企業家精神に富む若手人材の育成活動をそれぞれ行ってきた。一方科学研究費補助金などによるプロジェクト的共同研究の場としての先導的研究オープンセンターが存在した。法人化を機にこれら3機関が統合され先端科学イノベーションセンターと改組された。この統合されたセンターが産学連携の窓口となっている。図に示すように、大阪大学役員会直属の研究推進室(室長は副学長)の下に属する機関として上述の先端科学イノベーションセンターと知的財産本部とが併存し、特許取得、共同研究契約などで運営の協力を行うようになっている。
大阪大学は医学部、工学部などがある吹田キャンパス、基礎工学部、理学部などがある豊中キャンパス(いずれも郊外立地)及び社会人向け大学院などがある新設(2004年)の中之島センター(都心立地)からなる。中之島センターには技術移転を行うコンサルタント室が設けられている。知的財産本部は先端科学イノベーションセンターとともに吹田キャンパスにある。医学・薬学系と理工学系とでは研究のあり方、実用化までのプロセス、特許実務などで相違点が多い。また総合大学の場合、各学部それぞれに自立性が強く、キャンパスまたは研究施設が複数地域に散在することも多い。このため一部の大学では産学連携、技術移転又は特許の管理などを学部/施設ごとに半独立的に分散処理する体制を取るところが見られるが、大阪大学では知的財産ポリシーで
「知的財産の一元管理
本学は知的財産を全学の研究推進戦略、知的財産戦略に基づき一元管理する。これにより、本学の使命、理念との一貫性を確保した上で、その活用の推進を図る。 また、知的財産本部を設置し全学的な一元化管理体制を整備確立する。」
と明記して、知的財産の一元的管理を行って、外部からのアクセスのしやすさ、仕組みの分かりやすさを重視し、また学内での平等感の維持を図っている。
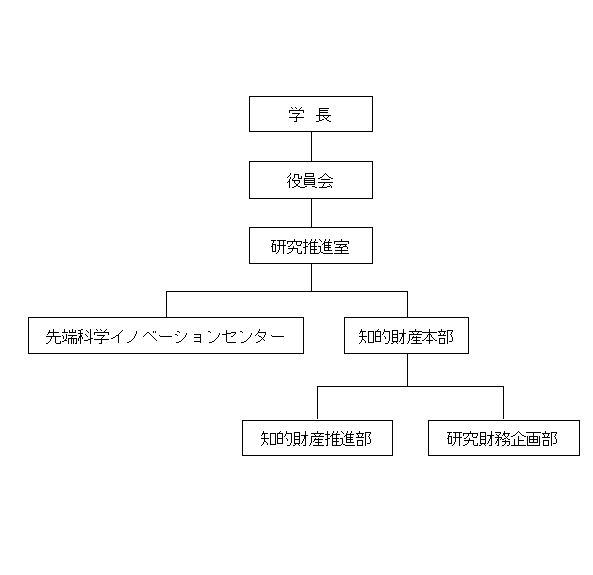
3.知的財産本部と弁理士
大阪大学の知的財産本部は2003年10月に立ち上げられた。発明の掘り起こし、相談、出願及びマーケティングなどを担当する知的財産推進部と、そのサポートなどを行う研究財務企画部との2部構成で、スタッフは教授2名、助教授1名、および電気関係メーカ、製薬会社から転じた特任教授4名と若干名の事務職員である。顧問スタッフは弁理士3名、公認会計士1名、及び弁護士2名である。
私を含めて3名の弁理士は当初特任教授として徴用された。そして法人化までの半年間、知的財産ポリシー及び発明規定の策定の協力、知的財産本部構築ための支援並びに教育・啓発用の資料作成などを行った。
発明相談はTLOのスタッフと共に随時行っているが、ここに一つ問題がある。相談業務では当然に発明の内容を知ることになり、これについては弁理士としての守秘義務を課せられることになる。大学での相談に係る発明は他施設での相談内容と比較して高度な技術であることが一般的である。これは弁理士が日常的に特許出願業務を受任している大企業の発明の水準と同等以上であり、技術分野が重なる場合の顧客競合の問題が懸念されるところである。大学は製造・販売をしないので企業とは直接競合しないから問題とすることはない、などの認識は誤りである。先に大学で相談を受けたのと同一又は類似の発明について企業から出願依頼を受けた場合の対処はどのようにすべきか。企業には最小限の事情を伝えて受任を辞退することが必要であろう。一方、その時点で大学の発明が未出願であったとしても、大学の発明者に出願を急がせるなどの助言もなし得ない。大学の知的財産部門に関与する弁理士はこのあたりのことを十分に認識しておくべきである。
法人化後は発明相談だけではなく、出願の適否判断などのために発明記述書を目にする機会が増えることとなる。また出願の可否を決定する発言をすることも少なくないはずである。発明相談、発明記述書審査及び特許出願判定会議への意見具申などに携わった大学発の発明を、自らの手で特許出願することとなれば、一連のプロセスに携われて素直な感覚では大いに喜ばしいところである。しかしながら大学内スタッフとしての特許出願可否判定は、出願代理による自らの利益誘導にもつながりかねないと言う見方がある。これが今ひとつの問題である。
法人化を一応のタイムリミットとする知的財産本部の立ち上げが完了したこと、上述のようなデリケートな問題が存在することなどを理由に、3名の弁理士は特任教授職を辞し、顧問として、より自由な立場から大阪大学知的財産本部をサポートして行くことになったのである。
4.発明の取り扱い
大阪大学で生まれた知的財産、特に発明は知的財産ポリシーまたはこれに基づいて制定された発明規定によって次のように取り扱われる。
まず、知的財産ポリシーは
「教職員等は、その職務に関連して行った研究成果が知的財産に該当すると認めるときは、論文学会発表等の公開に先立ち速やかに書面により本学に届け出なければならない。」
と規定して届け出を義務づけている。(届け出が論文学会発表に優先することを明記しているが、定着までには時間が必要であると思われる。この問題は5(1)で述べる。)このようにして届け出られた発明は職務発明としての取り扱いを受ける。即ち
「本学で教職員等により創作された職務上の研究成果に基づく知的財産に係る権利は原則的に本学が承継し本学に帰属する。」
と規定されているが、実際に承継するか否かは発明委員会が新規性、進歩性、市場性、学術的インパクトを評価して決定する。大学が企業と異なる点の一つは製造・販売を行わないことであり、ビジネス上の具体的競争相手はいないから、いわゆる防衛出願の必要性は無い。また現段階では十分な特許取得のための財務的基盤もない。このような理由から大学が承継しない発明が少なからず存在することになる。研究者にしてみればそのまま埋もれさせてしまうには惜しいと考える発明があり得る。そこで知的財産ポリシーは
「本学が承継しないと決定した知的財産に係る権利は創作した教職員等に帰属する。」
と規定して、発明者に、自ら出願するとか、企業と提携するとか、自由な処分を行える道を確保している。
企業との共同研究の場合には契約に従い企業との共同出願となるのが普通である。この場合、共同権利者の大学は特許製品の製造・販売などを行わないから、いわゆる、不実施の補償を共同権利者の企業から得る事としている。
大学の独自研究による場合は、大学自らの特許出願が原則ではあるが、マーケティングなどを考慮してTLOまたは技術移転支援企業へ特許を受ける権利を譲渡してそこからの出願と言うこともある。
発明者に対する報奨は出願時及び登録時に一定金額が支払われるほか、運用、処分によって収入が得られた場合には、出願などに要した経費を収入から差し引いた残額の一部が発明者及び研究室に配分される。例えば大阪大学が権利者である場合、発明者が残額の1/3、研究室が1/6と定めている。この仕組みは、大学発の発明がTLOで権利化されて収入が得られた場合の分配ルールに準じて定められたものである。
大学が許諾する実施権は非独占的実施権を原則とし、独占的実施権を付与する場合でも許諾期間は出願後10年を超えない事としている。これは共同研究又は受託研究の場合においても同様である。発明者がベンチャーを起こす場合には独占的実施権を与えるなど優遇的配慮がなされる。
5.大学発の発明がかかえる問題
以下には日頃接することが多くなった大学発の発明にまつわる2,3の問題点を考えてみたい。これらはひとり大阪大学だけの問題ではなく他大学でも散見されたことである。
(1)新規性喪失
知的財産の重視が叫ばれ、その活用、例えば大学発ベンチャーの創業が督励されても大学人の本分は研究(そして教育)であることに変わりはない。昨今の大学の知的財産重視施策に批判的な意見があるが、大学の研究者はいい意味で施策に影響されることなく、極めて健全に地道な研究を積み上げ、学会で発表し、または論文に纏めるという、研究者として不可欠なことをしっかりとこなしている。そうした研究の成果の中から実用化の花が咲きそうなもの、そして大学の研究成果の特徴的な点であるが、発見に近い技術などを拾い出して、発明記述書を起こしている、と言うのが実情であると観察される。
しかし、学会、論文重視の意識のために順序の間違いが起こるのである。最近遭遇した事例の一つを紹介すると、アメリカの学会へ予稿集の原稿を投稿したところ、学会開催日又は予稿集発刊日よりも3ヶ月も早くインターネットで公開されたというものである。従前はこのようなインターネットでの公開は行われなかった。また今回も、事前の公開許可を求めてくることもなかった(直前に「貴殿の論文が○月○日からURL XXX で見ることが出来ます」という電子メールが送られてきただけだそうである)。先発明主義のアメリカではこのような公開に神経を尖らせることはない。本事例は特許法第30条の適用が可能な事例ではあったが、これは日本国での救済が行われるだけであり、アメリカ以外では新規性喪失のために権利化できないことになる。技術分野にも依るが、外国での権利化ができない発明はライセンスする上で大きなハンデとなる。特許法第30条の存在を知っている研究者は少なくない。しかし論文発表を特許出願よりも優先してもよい、ということの潜在意識下での知識としてであって、そのような状況が技術移転の制約になり、大きな経済的果実を採り損なうとは考えていないのである。研究者の意識改革を望むと共に、大学の知的財産管理に携わる者は機会ある毎に「論文より特許が先」を研究者に教え込んで行かねばなるまい。
大学の研究者の人事評価は研究業績によるが、主として発表論文に依存する。評価指標として特許の内容、出願・取得件数も採用されることになれば研究者の意識も変わってくるに違いない。教授、助教授の公募に際して取得特許の情報を記載させる大学が一部に見られるようになったのは好ましい傾向である。
もう一つの事例は論文発表会である。企業と異なり、大学には研究の一翼を担うものの、大学とは雇用関係のない学生、院生というやっかいな存在がある。その発明の取り扱いについては後述するが、学生の卒業論文発表会、および院生の修士・博士論文発表会がある。前者は研究室単位など極めて小規模で行われるのが一般的であり、公開の可能性は実質的にないようである。ところが博士論文の発表会は公聴会と称して一般への公開を義務づけられている。修士論文の発表会も公聴会としているところが多いようである。公聴会は、当事者以外の聴講が拒まれないオープンな状況で開催されており、発表者の所属とは異なる教室の学生、院生、場合によっては全くの学外者が発表会場にはいることが考えられるのである。特許出願前の発明がこのような発表会で発表されたらどうなるのか。公聴会は大学(特許法第30条の学術団体に指定されていることが多い)が開催する研究集会ではなく、学部または学科が主催することが多く、この場合は同30条の適用は受けられない。
実際にあった事例は、修士論文発表の直前に特許出願が決まったが、時間的制約から発表までに出願を完了できないというものであった。新規性を維持するために、発明者又は発表者と発表会の聴講者との間で秘密保持の契約書を交わすことが考えられる。契約書案まで作成したが、多くの聴講者全員の記名捺印を得るのは現実的ではないと言うことで、結局特許出願対象となる部分を発表内容から除くこととした。
大学の「研究成果」が「知的財産」とならずに大学の外へ消えてゆくことにならないよう、知的財産部門のスタッフは注意深く目配りをしておく必要がある。
(2)学生、院生の関与
法人化後はこれまでと異なり大学で生まれた発明の特許を受ける権利は大学が所有する(機関帰属と称している)ことになった。この権利の承継で問題となるのは学生又は院生が発明者の一部又は全部となった発明である。一部の院生は大学に雇用されているので、その場合は教官と同様の扱いを受けることになる。即ちこの院生が関与した発明は原則的に教官のみでなした発明と同様、職務発明の様に扱われる。
これに対して、大学に雇用されていない一般的な学生又は院生にはどのように対応すべきか。大阪大学の場合、知的財産ポリシーは以下のように定めている。
「学生の創作した知的財産
本学の学生が本学または公の経費または設備を用いて行った研究により創作した知的財産に係る権利については、本学は、学生との間に契約を締結することにより、学生から譲渡を受けることができるものとする。
ただし、学生のうち本学が採用するものであって、雇用にあたりその者が創作する職務発明等を含む知的財産に係る権利について契約がなされている者は教職員等に含まれ、本条は適用されない。」
そして先に記載した発明者への報奨については
「学生が本学に譲渡した知的財産に係る権利について、出願、登録、並びに収入があった場合は、本学は学生に補償金を教職員等に準じて支払う。」
と、手厚い規定を用意している。
特許法第35条に定める職務発明の規定は、発明者が法人の従業者等であることを要件としている。雇用関係がない学生・院生は当然にこの要件を満たさない。そこでこのポリシーに規定したように個別の契約締結が必要となるのである。
大学発ベンチャーのニュースが新聞を賑わし、学生の起業を支援する学内組織も用意されている環境下では、学生が特許を受ける権利を大学に譲渡しない、と言うケースも起こりうる。このような場合は大学と学生が特許の共同出願人となるわけであるが、学部学生が研究に取り組むようになるのは一般に4回生からであろうから、発明の完成後、短い場合は1年以内で大学を去ることになる。在学中はともかくも、卒業生に、中間手続きに対する義務(手続補正書・意見書の作成のための責任ある指示、及び費用の負担など)を果たさせ、特許料の支払いを行わせる様に、大学の知的財産部門が卒業生を追跡管理していくのは決して容易ではない、と思われる。出願前に適当な対価を支払って大学に帰属させるか、暫時行方不明となっても支障がないように、当面の費用を預託させ、また中間手続きは大学に一任する旨の念書を取っておく等、強制できないにしても、何らかの便法を考えておく必要があると思われる。
企業在籍者が共同研究の研究員として大学内で研究に従事することがある。、この場合、不用意に他の研究者の研究にアクセスされることがないように物理的な対策を大学が講じておくことが望まれるが、現実はそのような状況にないようである。学生・院生は大学での研究に深く関わり合う。このような状況で研究の成果が特許出願されることなく漏洩したり、冒認出願されたりすることがないように学生・院生に対して守秘義務を課すことが不可欠であると考えられる。社会人学生・院生も存在するので対策が急がれる。
大学が企業と共同研究契約を結ぶ場合、その条項に両者が機密保持する旨の規定が盛り込まれる。大学は共同研究に携わる学生・院生に機密保持を守らせる管理責任を負うのは当然である。それにとどまらず、他の学生・院生についても同様の管理責任を負う事になる。学生・院生は教室(学科)内を自由に移動するし、同研究室内では他グループの研究にも興味を示す。従って、共同研究を受け入れる教室全体としての機密保持の為の管理が必要である。
学生・院生は長くとも数年以内に大学を去ることが殆どである。しかも、共同研究のパートナー企業の競争相手の企業に就職すると言うのがほとんどであろう。企業に勤務していた技術者が退職後に競合他社に転籍することに一定の制約の条件で禁じる事は可能である。学生・院生は在学中に給与を得ていたわけではないからこのような競業避止義務を負うとは考えにくいし、現実的ではない。共同研究では共同研究終了後も所定年限、守秘義務を課すことがある。学生・院生の場合も卒業後の年数を限って、守秘義務を課すのが実際的な解決方法ではないであろうか。
なお、学生の発明の取り扱いについては
苗村博子・牟礼大介「学生の研究成果の取り扱い」 L&T No.26(2005年1月)65頁
が、特許法のみならず、労働法、消費者契約法(学生を大学が提供する教育のサービスの顧客と見る)憲法(職業選択の自由)及び不正競争防止法などの観点から詳しい考察を行っている。
(3)ライセンスに際しての障碍
この問題の一つは(1)に指摘した特許法第30条適用出願である。特許権が存在する国では権利者は製造又は販売などの独占権を有する。従って日本で特許権を取得した場合には、日本国での製造販売、第3国で製造したものの輸入などを独占し得る。先に記載したように、米国での特許取得は可能であるから、これができた場合は、アメリカでの製造販売、及び日米以外で製造したものの米国への輸入の独占が加わる。特許法第30条を適用しての出願の場合、アメリカへの出願で特許を取得したとしても、これだけの権利しか得られないから、世界を消費地とする薬品などは僅かな人口を対象とするマーケットにしか特許の効力が及ばず、経済的に価値の低い権利ということになる。機械の特許の場合も、特許法第30条適用出願であるときは、第3者による韓国製造で欧州市場へとか、台湾製造で中国本土の市場へ等と言うことが起こり、不本意な結果を招くことになる。企業は競合企業がある国及び市場がある国を視野に入れて外国特許出願をする。このような企業の行動様式に合致していない権利はライセンス供与しにくいということになる。日本企業の特許部門が30条適用出願を原則認めないとする強い姿勢を研究開発部門に示し、これを定着させて久しい。大学も研究者に対する啓発活動により急ぎ対応する必要がある。
次にライセンサーとしての大学の姿勢が問題である。大学から特許権の通常実施兼の許諾を受けた企業が、競合企業の特許権侵害行為を発見した場合、権利共有者または専用実施権者でない限り、自らはこの侵害行為に対する措置をとれないので、大学にまずは警告などの措置を取って欲しいと要求することになる。そして相手が侵害を認めず、侵害行為を止めない場合は法的対応を望むのはライセンシーとして当然とも言える。
大学はこのような対応の要求に応えることが可能であろうか。大学は知的財産の創出はできてもこれを守っていく体制は十分とは言えない。実施権許諾交渉は民間企業同士の場合、泥臭い交渉が必要なことが多いが、大学が企業にライセンスを与える場合、金額面はさておき、他の条件で面倒が起こることは少ないと考えられる。それは教授を初めとする研究者に対する尊敬の念が背後にあることと、大学が製造・販売などを行う競業者でないことに依る。従って大学の契約担当者は契約をさほどの困難無しに纏めることが出来る。これに対して侵害者は尊敬の念などとは無関係であるから、権利行使のための作業は民間企業が権利者である場合と同様、タフな仕事とならざるを得ない。
どのように対応してくれるのか、最悪の場合は訴訟で差し止めをしてくれるのか、ライセンシーの不安は尽きない。こうした不安材料が、企業が大学からライセンスを受けようとする場合に腰が引ける要因となる。大阪大学の場合、知的財産ポリシーに
「侵害、訴訟等への対応
本学は、研究成果の活用や社会への移転を進めるために、本学の所有する知的財産権の侵害、訴訟に対して、TLOなどの外部機関、共有特許権者、特許実施権者等と連携して適切な対策を講じるものとする。」
と明記して、安心して実施権許諾を受けられる体制にあることをアピールしている。小企業にとって敷居が高い国立大学、というイメージを崩してライセンスビジネスを行いやすくする上で有効な姿勢であると評価したい。
6.あとがき
大学の研究は経済的利益を得るために行うのではない。また研究成果はなるべく多く社会に還元されることが望まれる。このような観点からは経済的対価は必須ではなく、特許取得にさほどの注力をする必要がないということになる。しかしこのような考え方は誤りである。誰もが自由に研究成果を利用できるのは一見好ましいように見えるが、研究成果を実用化するには生産技術などの開発に投資が必要であり、複数の企業の参入があると、この投資に見合う利益の確保が見込めず、結局は事業化には至らないことになってしまう。技術移転を受けた民間企業はその技術が特許で守られていればこそ安心して製造・販売のための投資が行えるのである。この状況は、多量の水が堰堤で守られて高い水位を保てばこそ水力発電として効率よくエネルギー利用が図れるのに対し、流れるに任せれば「自然の恵み」に止まってしまうのに似ている。
共同研究の成果はパートナー企業の助力で特許出願から実用化まで円滑に行われる構図が見えている。これは法人化以前の実績に照らしての予測的判断である。しかし、特許発明の実施に対する不実施の補償金を大学が企業に求める仕組みになっている点が以前と異なっており、これについての影響がどのような形で現れてくるかは不明である。楽観的に見れば高い研究レベルを維持している限り、共同研究の申し込みが絶えず、不実施補償金により大学、研究室が潤うということになるが、以前は不要であった不実施補償分の負担増を共同研究費の削減という形でつじつまを合わせる企業も出るかもしれない。
大学独自の研究については、特許出願のための原資が不足していること、マーケティング体制が不備であること、大学発ベンチャーの経営、営業に携わるスタッフが足りないことなど、解決していくべき問題が山積している。
大学の知的財産業務に関わる弁理士は大学内外に相当数存在する。原資の制約から民間企業と異なり数少ない特許出願で知的財産を守り育てる、という基本的な部分での能力発揮は当然にしていかなければならないが、それに止まらず、企業人脈を生かしたマーケティングへの協力が望まれるところである。
|